子どものころに記憶をさかのぼると両親がコーヒーを楽しんでいた記憶があまりない。けれども台所の棚に銀色のパーコレーターがあったのを思い出した。ポット型のパーコレーター。ふたの部分が金属とガラス部分でできていたことを思い出す。今コーヒー用具専門店に行ってもなかなかパーコレーターのラインナップを見かけることが少ない。
このパーコレーターは父親や母親の趣味で台所にあったものと思われず、昔の両親の話の記憶をさかのぼってみると母方の祖母が戦前cafeを経営していたことを思い出した。母の話によればコーヒー豆がたくさんあったとのこと。これだ。両親の持ち物ではなく祖母の愛用品だったのかもしれない。その祖母に淹れてもらったコーヒーに砂糖をたくさんいれて飲んだ記憶がよみがえってきた。「そうだ、おばあちゃんに淹れてもらったんだ」今から考えれば60年以上前のことである。今よりもはるかに豊かな時代だったように思われる。まだ道路は舗装されていないところも多かった。バスはボンネットバスでウインカーはランプの点滅ではなく真っ赤なバーが飛び出していたように思う。普段着はつぎあてのあたっている服が普通だったが、「よそ行きの服」というのがあった。
「よそ行きの服」とは、お出かけ用の服である。今のようにファストファッションなどない時代。すべて手作りの時代である。その手作りを仕立て屋さん(洋裁屋さん)に注文するのである。私の育った大津には「YOUSAIYA」という屋号の傘屋さんがあったくらいである。もともとは洋裁の注文を受けていたのだろうが大津祭のちょうちんや地蔵盆のちょうちん、国旗、学校の制服やランドセルまで売られていた。幼稚園の同級生の女の子がその家の娘だったし、彼女のおばさんは通っていた幼稚園の先生だったことも思い出した。余談ではあるがその「YOUSAIYA」は屋号を「シェルブール」に変えていた。店主のおしゃれ心と家業が傘専門店にしようとの意図なのか映画「シェルブールの雨傘」へのリスペクトだったのかもしれない。
ずいぶん話が横道にそれたが、よそ行きの服を誂えるのである。記憶をたどるとサスペンダーが共布の半ズボンをいくつも作ってもらっていた記憶がある。ブレザーも誂えだった。よそ行きの子供服はおしゃれ着なので泥汚れとは無縁の着方である。お出かけから帰ったらすぐ着替えてクリーニングに出すような暮らしぶりである。まさに豊かな暮らしというほかない。周囲はみんな豊かとはいえないつましい暮らしをしていたのだが、今と比べてみれば既製服ではなく注文服に袖を通すというのは豊かさにつながる。
そんな時代だからインスタントコーヒーも庶民の暮らしには登場せず、コーヒーを口にするには豆を挽いてということになるのが自然であったのだ。コーヒーの記憶をたどるうちに当時の暮らしのありようがどんどんわきでてくる。 つづく
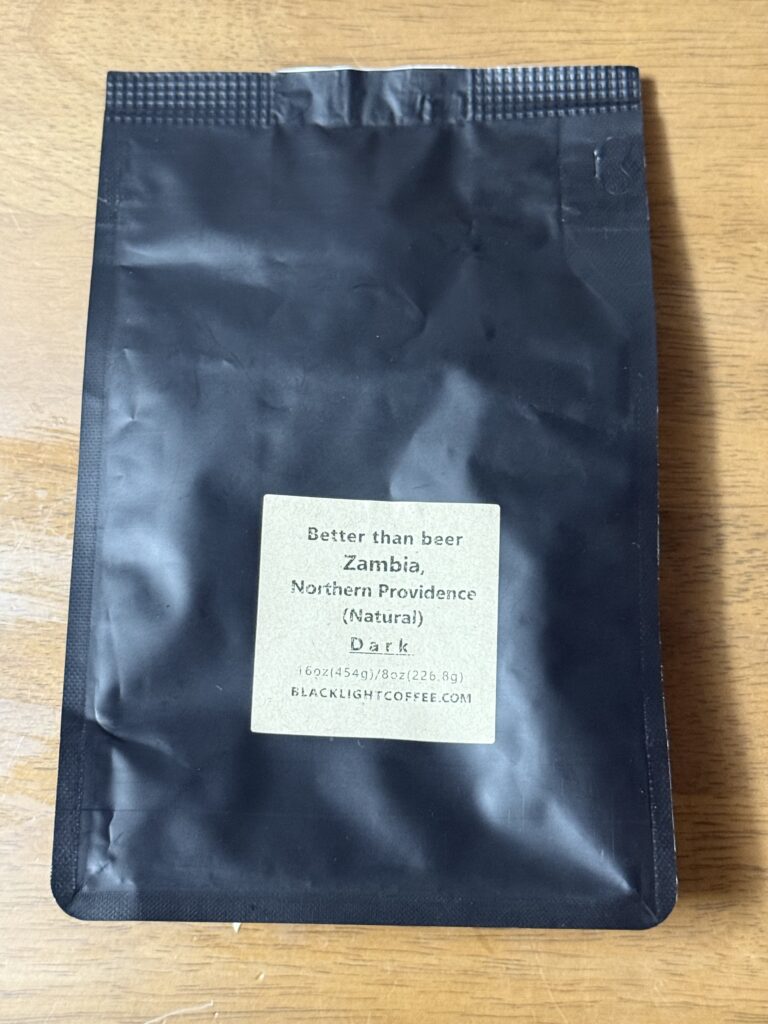

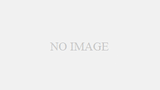
コメント